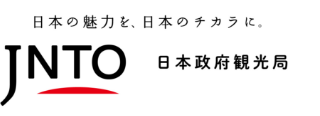2022年1月10日
農泊で地域活性化を。醤油蔵の再興を軸とした農村の取り組み(後編)

奈良県最古の醤油蔵を再興する際に農泊の視点を入れ、2020年8月に誕生したのが“泊まれる醤油蔵”と謳った「NIPPONIA 田原本 マルト醤油」です。この起ち上げには、醤油蔵の再興だけでなく、地域全体における協力体制の構築や魅力の再発見など、多くの取り組みが行われました。こちらの記事では、醤油蔵再興への経緯や地域における具体的な施策などについて、農泊事業を推進する田原本町川東地域資源活用協議会の会長であり、マルト醤油の18代目当主でもある木村浩幸氏に、前編に引き続きお話を伺いました。
(前編)はこちらから
ローカルとグローバルの視点が地域の魅力発見につながる
—3年間通った、観光ビジネス講座で得たものについて教えてください。
「熊野古道の復活や世界遺産登録に尽力された刀根浩志さんから観光ビジネスのイロハを教わりました。彼は『NPO法人ほんまもん体験倶楽部』の事務局長でもあり、豊かな自然環境や田舎でしか体験できないことを『ほんまもん体験』と呼んで、ほんまもん体験を通じた地域の活性化を提言されていました。
その考え方に心惹かれ、醤油蔵の再興を通じた事業を思い浮かべるようになった私に、刀根さんが『創業を考えているのなら、よろず支援拠点に相談に行ってみたらいい』と教えてくださいました」
—よろず支援拠点からはどんなアドバイスがありましたか?
「よろず支援拠点は、中小企業庁が各都道府県に1箇所ずつ設置している経営指南窓口です。その名の通り、起業の相談から総合的・先進的な経営アドバイスまでさまざまな内容の相談に応じてくれる場所です。私が構想している、地域を生かすこと、醤油蔵を復活させること、また醤油蔵の復活を主軸とした地域ならではの体験や文化を感じることができる体験型宿泊施設を開設したいと話したところ、『それがどれだけの人の関心を呼んで応援してもらえるか、バロメーターを確認してみたらいいのではないか』とアドバイスをいただき、奈良県が毎年開催しているビジネスコンテストに出場することになりました。
全国254件の応募の中から創業部門で優勝し、農村部で体験することに価値や魅力があるのではないかと自信を持つことができました。また、ここから田原本町川東地域資源活用協議会の構成員である株式会社NOTE奈良ともつながっていきました」
—株式会社NOTEは全国で古民家の再生を手掛けている会社ですね。
「NOTEは私にとって大きな存在です。簡単に言うと、私はローカルな視点で川東地域を見て、地域の良さをどう伝えたらいいのかを軸に物事を考えています。大阪で働いていましたから、外からの視点はあるにはありますが、全国的な視野はない訳です。
一方NOTEは、少しオーバーな言い方になりますが、グローバルつまり広い視点で物事を見ています。地域を発展させる事業には、この2つの視点が必要なのではないでしょうか。今、世の中でどういうことが起きているのか、なにが求められているのかをタイムリーに、また敏感に感じながら、その土地に根ざしたものを発掘する。その両輪があって初めて、吸引力のある魅力を見つけることができるのではないかと思います。そういう点で、NOTEは地域にとって欠かせない存在だと感じています」
醸造職人が寝泊まりをしていた蔵を活用した客室
農泊のポイントは、どこに宿泊してもらうかよりも、地域の魅力をどこまで盛り込めるか
—「NIPPONIA 田原本 マルト醤油」では、どのような体験ができるのでしょうか?
「もともと蔵だったところに泊まれる宿泊施設はたくさんあると思いますが、“泊まれる醤油蔵”というキャッチコピーの通り、実際に醸造が行われている館内に宿泊できる場所はそうそうないのではないかと思います。
醤油蔵に足を踏み入れれば醤油のほのかな香りを感じることができるでしょう。醤油は生きていますから、訪れる季節が変われば、醤油の香りをはじめ、その変化までわかるかもしれません。滞在のご予約をいただいたお客様には“旅人から蔵人へ”というタイトルでメールを送信し、宿泊への期待感も醸成しています。
またお客様は、醸造蔵で醤油しぼり体験もできます。晒し(さらし)に包んだ醤油醪(もろみ)を“ところてん突き”にセットして、棒で押すだけのシンプルな体験ですが、大きな太い梁が使われた実際に醤油が作られている現場での体験は、本当にお客様に醤油の奥深い世界を感じていただけていると思います。
当初は小さなお子さんは飽きて、走り回ったり、他のことをしだしたりしてしまうかと心配していましたが、子どもたちは知らない世界を体験することにとても興味を持ってくれます。一滴一滴ピタッピタッとゆっくり醤油が落ちてくるさまは、原材料までこの土地で生まれたものということも相まって、とても貴重に感じてくれるようです。最後は自分でしぼった醤油を焼いたくずもちにかけて食べますが、焦げた醤油の香りとともに鮮明に記憶に残る体験になっていると思います」
—他にはどんな体験ができますか?
「少し早起きしていただくことになりますが、朝の7時30分から稲作の神様が祀られている村屋神社に朝参りする体験メニューがあります。
これは、地域を歩くというのがポイント。この時間はちょうど農家さんが畑に出て作業していることが多いので、農家さんとコミュニケーションをとることができます。挨拶をしたり、作物について問いかけたり、地域の人たちとの触れ合いを通じて、まるでここが自分のふるさとかのように、地域全体に受け入れてもらっているような温かな感情が生まれているのではないかと思っています。
こうして朝参りした後の朝食はまた格別です。地元の農産品を口にすること自体もひとつの大きな経験ですが、さらにどんな風に愛情を込めてこれらが作られているのかを感じて食べる朝食は、普段都会で食べている朝食と一味も二味も異なるのではないかと思います。
醤油蔵に宿泊するという非日常的な体験はもちろんのこと、地域全体で受け入れることができるのは、3年かけて地域の皆さんと意見を本音で交わし合い、すり合わせ、納得していただいた上で事業をスタートさせたからこそです。農泊というのはどこに泊まるかよりも、その地域に根ざしたどんな体験ができるか、地域の人の想いや魅力をどれだけ込められるかが大きなポイントなのだと私は思っています」
朝参りで訪れる村屋神社
農村でゆっくり過ごすことに価値を見出す
—コロナ禍での開業となりましたが、これをどのように受けとめていますか?
「全国的なニュースにもなったように、コロナ禍当初は予定していた資材が集まらなかったりして、とても大変で不安なことばかりでした。しかしいざ開業してしまうと、人流が少ない中での開業はむしろ私たちにとっては良かったのかもしれないと思うようになりました。コロナ禍でなかったら、急激な人の波が地域の人たちとハレーションを起こしてしまったかもしれませんが、ゆっくりと時間が流れる中でちょっとずつ宿泊客がやって来るので、地域の人たちもその変化に大きく戸惑うことはあまりなかったと思います。
今、個人個人が旅に求めていることが変わりつつあり、旅の概念自体も変化していると感じています。これまでは観光資源があるところに出かけて、限りある時間いっぱい使って、見たり、食べたり、遊んだりすることを目的としていた旅が多かったと思います。しかし、これまで私たちのところに来てくださったお客様からのフィードバックを見ると、忙しい日常から離れ、農村でゆっくり過ごすことに価値を見出していらっしゃいました。のんびりすることや、スローフードを地産地消で楽しむといったことを贅沢と捉えている。そのことに私たちも勇気づけられています」
—インバウンドの受け入れについては、どのように考えていますか?
「この農泊事業の中心となるマルト醤油蔵は、日本の食卓と切り離すことができない醤油という調味料が作られる現場です。醤油醸造している館内に宿泊し、作り方を知り、さらにはその原材料が採れる場所にも足を運んで、大和の醤油醸造文化に触れる。それを古代文明が栄えた奈良で体験するのはなかなか複層的で、他ではできない日本の原点を知るようなおもしろい体験ではないでしょうか。
今後インバウンドがいつ戻るのかはわかりませんが、日本の農村の良さを海外の人にもぜひ知ってもらいたいですし、その準備もしっかり行っていくつもりです。ただ宣伝については、あまり性急に露出を図るのではなく、旅する人の心に徐々にわれわれの印象が届くような、そんな媒体を選んでいきたいと考えています」
(前編)はこちらから
マルト醤油18代目当主 木村浩幸
1976年生まれ、田原本町で生まれ育つ。京都産業大学経営学部卒業後、大阪のアパレル関係会社に勤務。2001年に祖父が亡くなったことをきっかけに、家業であり約70年前に閉業したマルト醤油の再興や地域の発展に思いを巡らすようになる。2011年から観光ビジネス講座を受講するなど勉強と経験を積み重ね、2020年8月に「NIPPONIA 田原本 マルト醤油」を創業する。